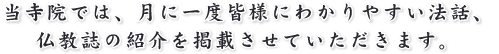最近は毎日のように簡単に人が殺されるこうした事件が報道されています。
日本に限らず世界中で悲しく、痛ましい出来事です。私たち人間はどうしてこんないとも簡単に人の命を奪ってしまうのでしょうか?
お釈迦様は、この様におっしゃっています。
「すべてのものは暴力におびえ、すべてのものは死を恐れる。己が身にひき比べて殺してはならぬ、殺されてはならぬ。
すべてのものは暴力におびえる。すべての生き物にとっていのちは愛いとしい。
己が身にひき比べて、殺してはならぬ、殺されてはならぬ。」
古来、仏教思想には人間がしてはならない5つの戒めがありました。その第1が「不殺生戒ふせっしょうかい」です。
人間は命が保証されませんと、自分も生きていけるという保証がありません。自分自身が生きていくことを願うならば、同時にほかの人びとの命もまた保証しなければなりません。それが人間として最低限の規範だったのです。
ところで、この問題について私が大変疑問に思うのは、そもそも、「なぜ、人を殺してはならないのか?」というようなことが議論されなければならないのかと言う事です。
この原因を考えたとき、そこには「命」というものを理屈ではなくて実感として感じることがない、という実態があるのではないかと考えます。
日本では「畳の上で死にたい」と言われました。少し前までは病院で息を引き取る人の数よりも、自宅で亡くなる人の数ほうがずっと多かったのです。そこでは、家族が亡くなる人の手を取り、この世の別れをすることができました。
大勢の家族が一緒に暮らしていて、しかも寿命が今よりずっと短かったころには、親族の臨終に立ち会うことはけっして珍しいものではありませんでした。子どもたちは、「死」という厳粛な事実を目の当たりにすることによって、命について感じ取り、考えることが普通でした。
では、現在はどうでしょう?
まず、現在は生活の中には重い病人があまりいません。病気になると皆入院し、死を迎えるのは大抵家ではなく病院です。医療施設が充実し、誰もが病院で治療を受けられるようになったことは確かに良いことですが、そのために、人が亡くなるという場に立ち会う機会が少なくなったことも事実です。
また、100歳以上の男性が1万人を超えるなど、超高齢化社会になって老人の数は確実に増えていますが、3世帯以上の家族が同居することは非常に少なくなりました。おじいさんやおばあさんのお葬式に出ることはあっても、実際に亡くなっていく様子を見ることはほとんどないでしょう。
つまり、昔と違って、家族で死を実感として捉える機会は極端に減っているのです。
人が死んでいく様子を実際に見ていないということは、死の悲しみや寂しさ、喪失感と言った事を味わったことがないという事です。ひいては、命の重さも命の尊さも感じ取らずに子供たちは成長するという事になってしまいます。
死を受容するこころが希薄になったと言えるでしょう。
「死」が自分にとって遠い出来事ではなく、身近なところにあったときには、「なぜ人を殺してはならないのか?」ということを問う人などいませんでした。聞かなくても誰でもが知っている、個人個人が自分で感じ取ってわかっていることだったからです。
そういう意味では、この問いかけをする人こそ、すでに命を実感として感じていないのではないでしょうか。死に伴う肉体的な痛み、心の痛みを味わったことのある人ならば、こういう疑問を投げかけようとはしないと思います。
仏教では、広く生物的生命、身体、さらには人間の心を含めて「命」と言っています。
その「命」は恵まれたものであって、自分であれ、他人であれ、私的なものではない。というのが仏教の考え方です。
「命」は自分で好き勝手にできるものではない、品物のように売ったり買ったり、捨てたり拾ったりできるものではないのです。
ひとりの人間が存在するとき、その背後には、長い命の流れ、命の連鎖といったものが必ずあります。両親、そのまた両親と、祖先から連綿と続いてきた命のつながりによって、ここに生きていることができるのです。
私たちは母親から生まれたときから数えて何歳、と考えますが、地球上に生命が誕生してからと考えると、35億年の命の積み重ねで自分が存在するのだというように考えることができるのではないでしょうか。
今日という時代に限定して、横のつながりを考えてみまても、人はひとりでは生きることはできません。家族、親戚、友人、仲間、その他様々な人間同士の繋がりによって生きています。
「人間が生きているということは、単に親兄弟の血のつながりがある、命の繋がりがあるということではなく、この世に生まれたものは、人間だけでなく、動物も植物も大きな命を分けあって生きている」のです。
人が殺されるということは、そういうあらゆる繋がりが、すべて絶ち切られてしまうということなのです。
「命」は、粗末にできるものではないのです。「命」を粗末にしない世になる事を切に祈ります。